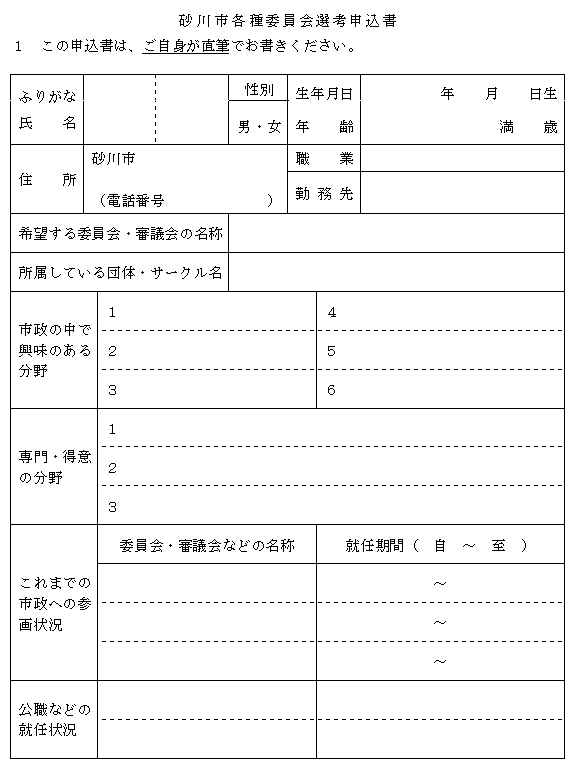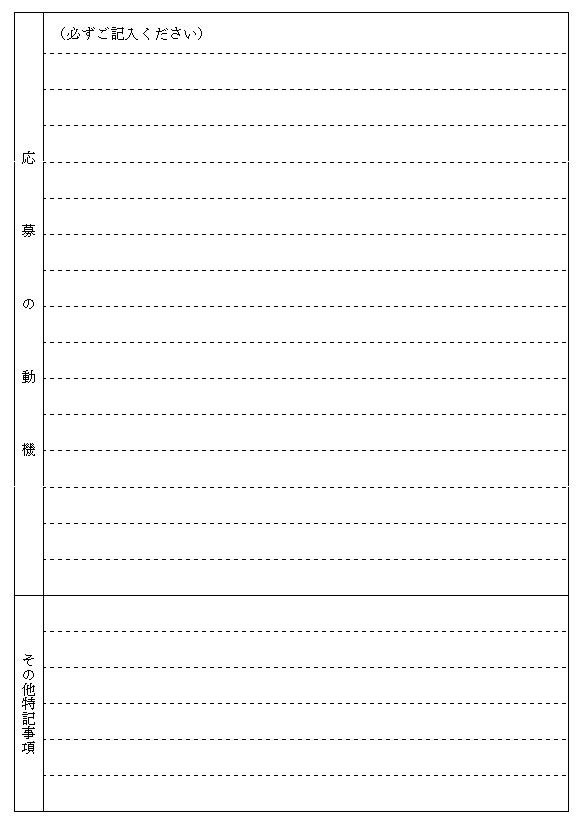第1条 この要綱は、市政の中立・公正性の確保及び市政への市民意思の反映を図るため、附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置・運営等について準拠すべき基本的事項を定めるものとする。
2 この要綱において「協議会等」とは、法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、市政に対する市民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するものをいう。ただし、次に掲げる「協議会等」については、除外するものとする。
(1) 協議会等の運営を市民が主体となって行っている市民(住民)組織的な性格を有するもので、協議会等の事務局のみが市の機関内部に置かれているもの
(2) その他この要綱の対象とすることが不適当なもの
第3条 附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の所掌事務は、設置目的及び審議事項が類似する附属機関等の設置を防ぐため、できるだけ広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置して弾力的、機能的な運営を図るものとする。
(2) 附属機関等の設置については、行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限るものとする。
(3) 附属機関等の委員の数は原則10人程度とし、所掌事務範囲の広い附属機関等については20人程度とする。ただし、法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。
(4) 臨時的な附属機関等については、設置期限を明示するものとする。
(5) 協議会等の設置の際には、その名称には、審議会、審査会、調査会など附属機関と紛らわしい表現は用いないものとする。
第4条 附属機関等の委員の選任については、当該附属機関等の設置目的を踏まえて広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任するものとし、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、特定の人が長期にわたって選任されることを避けつつも、審議等の経過や状況の把握に時間を要するものがあることにも配慮するものとする。
(2) 女性及び青年の市政への参加を積極的に推進し、特に女性については委員定数の30%程度とするように努める
(3) 市議会議員は、法令等に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合を除き、委員に選任しないものとする。
(4) 市職員は、法令に定めがある場合及び附属機関等の性質に照らしやむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。
(5) 同一人を委員として選任できる機関の数は、あて職の場合を除き5機関までとする。また、あて職の場合にあっても「代表」職に限定せず、重複選任をできるだけ避けるようにする。
2 前項第5号の規定については、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。
(1) 当該附属機関等の所掌事務に密接な関連を有する者や団体を代表する者及びこれらに準ずると認められる者である場合
(2) 専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合など特別な事情があると認められる場合
第5条 委員の任期は、法令に定めのあるものを除き、原則として2年とする。
第6条 砂川市の行政執行により多くの市民の意見を反映させるため、附属機関等の委員を公募する。
2 委員を公募する機関は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関等を除いたものとする。
3 公募枠は、委員定数の30%程度とするように努める。
4 委員の公募は、広報紙に掲載することによって行う。
5 公募委員の申し込みは、砂川市各種委員選考申込書(
様式第1号)により行う。
6 委員の申し込みをすることができるのは、本市に居住し、かつ、本市に住所を有する満20歳以上の者とする。
7 公募委員の選考は、書類選考その他の方法による。
(1) 選考の審査は、総務部長及び募集する附属機関の所管する部課長の合議による。
(2) 市長は、委嘱に際して重複委嘱を避けるよう努めなければならない。
8 委員を公募する附属機関等は、
別表のとおりとする。
第7条 附属機関等の会議は、原則として公開とする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) プライバシーに関する会議など、特に必要がある場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
3 附属機関等は会議を公開するに当たっては、事前に委員の意見を聴き公開の是非を決定するものとする。
4 会議を開催する場合は、広報等により、会議名、日時、場所等を事前に市民に周知するよう努めなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。
第8条 附属機関等の事務は担当課において処理するものとする。
第9条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
(2) 社会経済情勢や市民のニーズの変化により著しく役割が低下してきたもの
(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの
第10条 各部長は、新たに附属機関等を設置する場合若しくは既に設置されている附属機関等を廃止若しくは統合する場合又は附属機関等の委員の選任若しくは解任を行う場合は、総務課を経由して総務部長に合議するものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、運用に当たって必要な事項は別に定める。
2 第3条第3号、第4条及び第5条の規定については、附属機関等の委員の改選時から適用する。

様式第1号