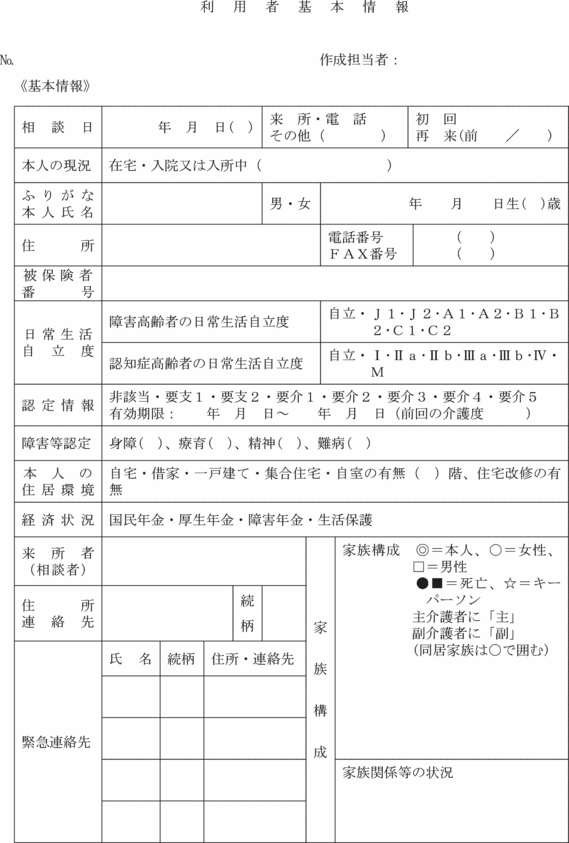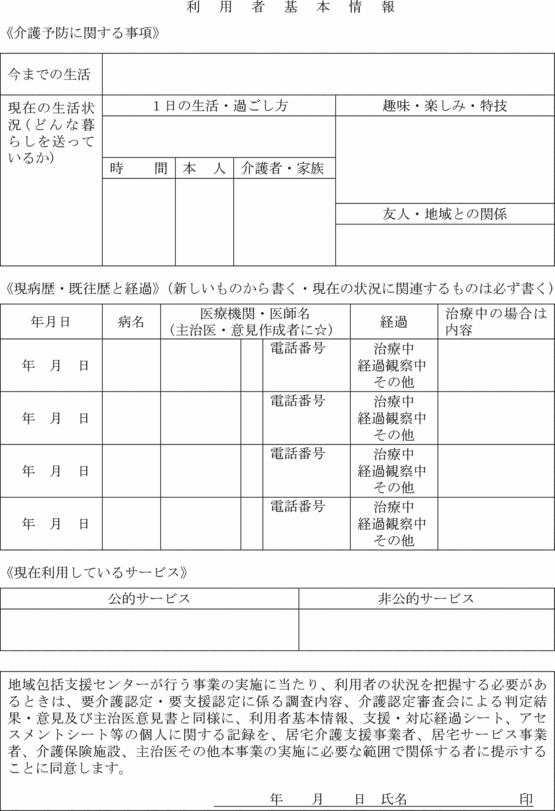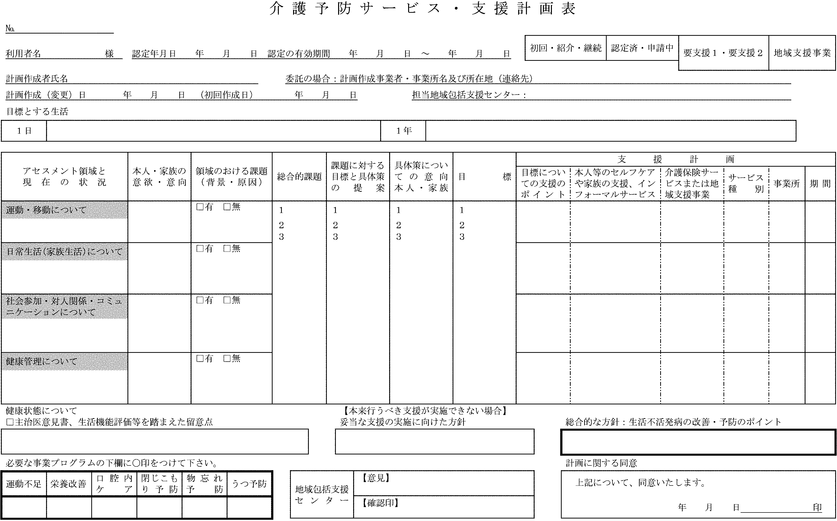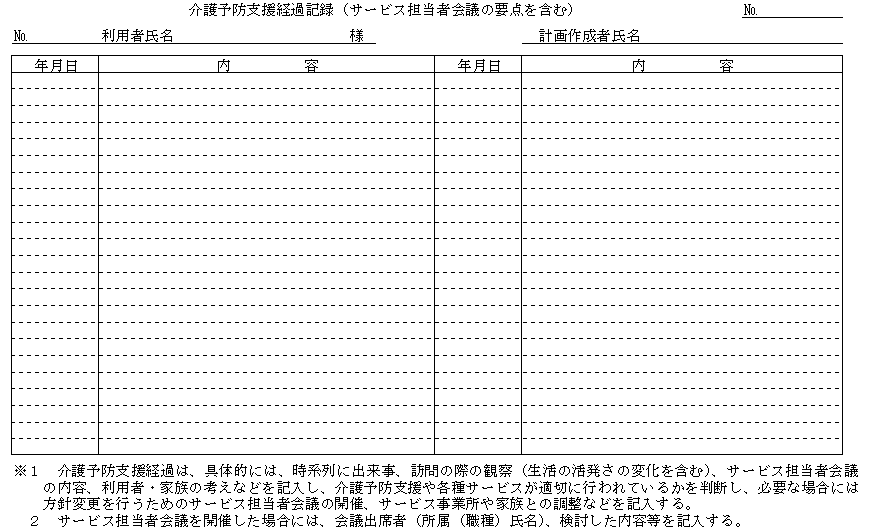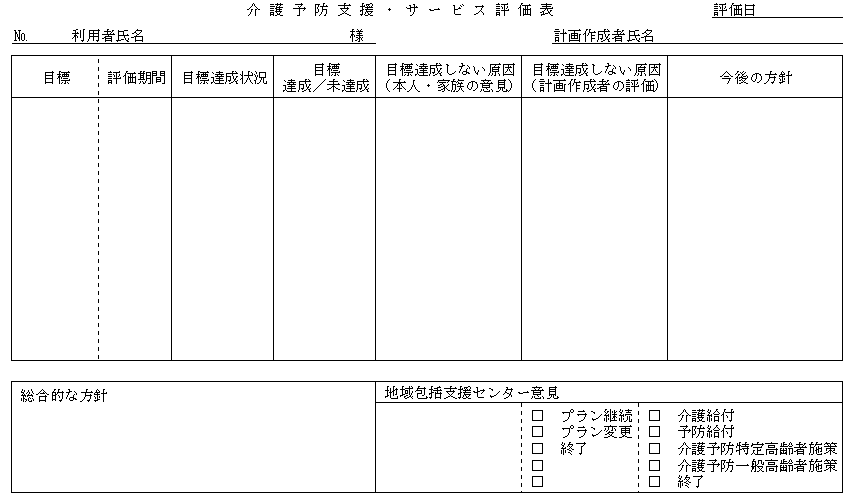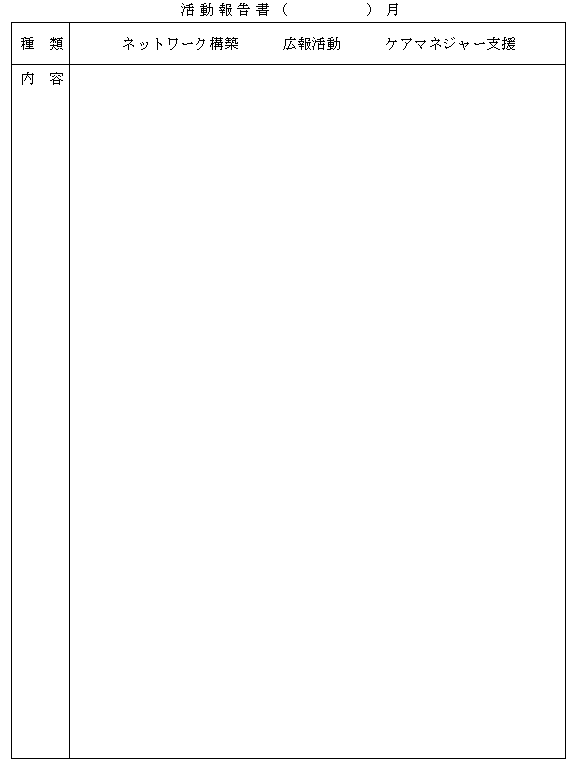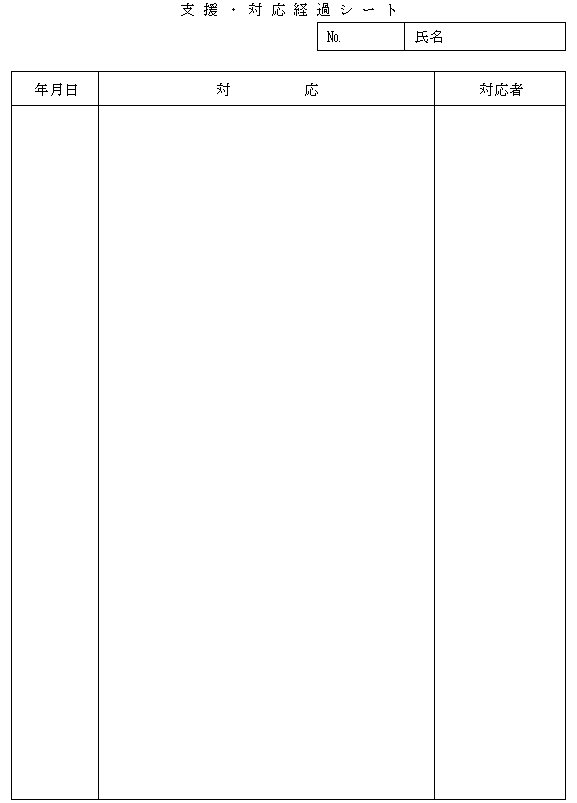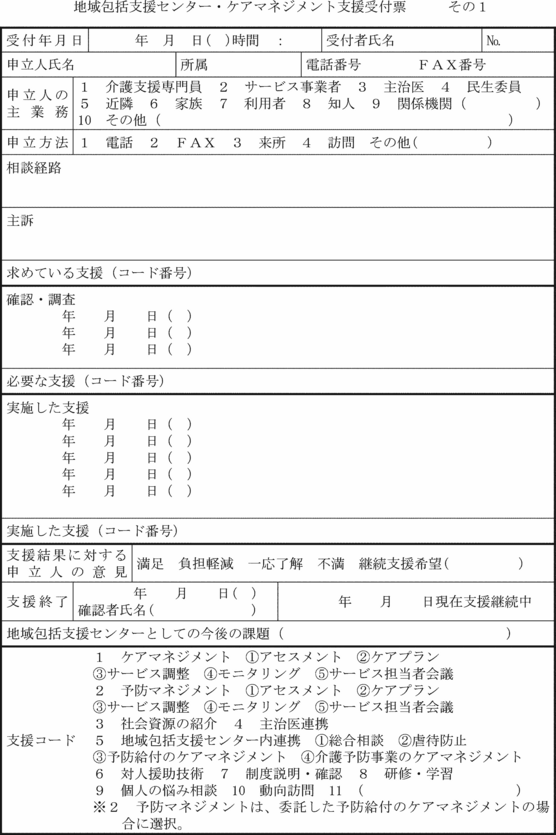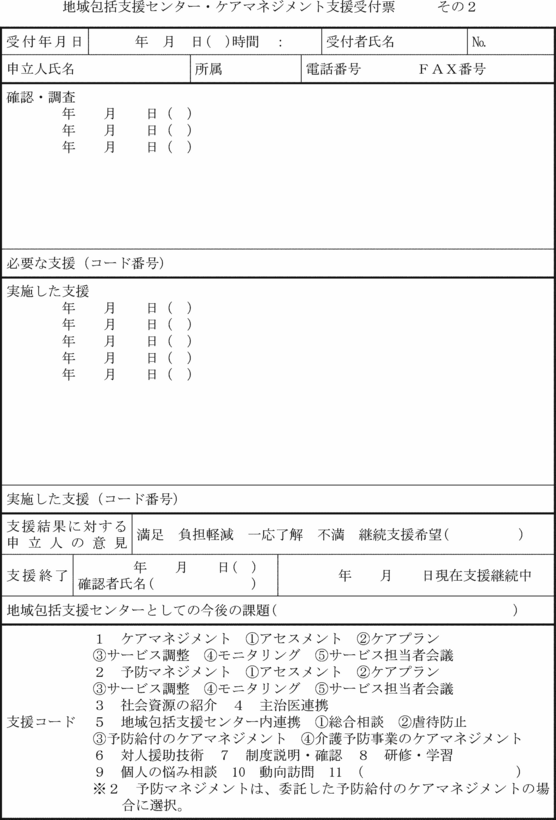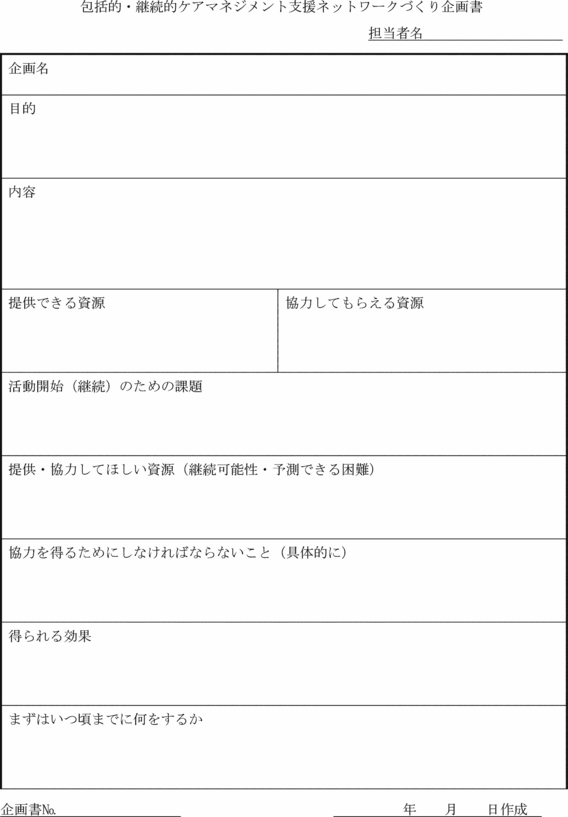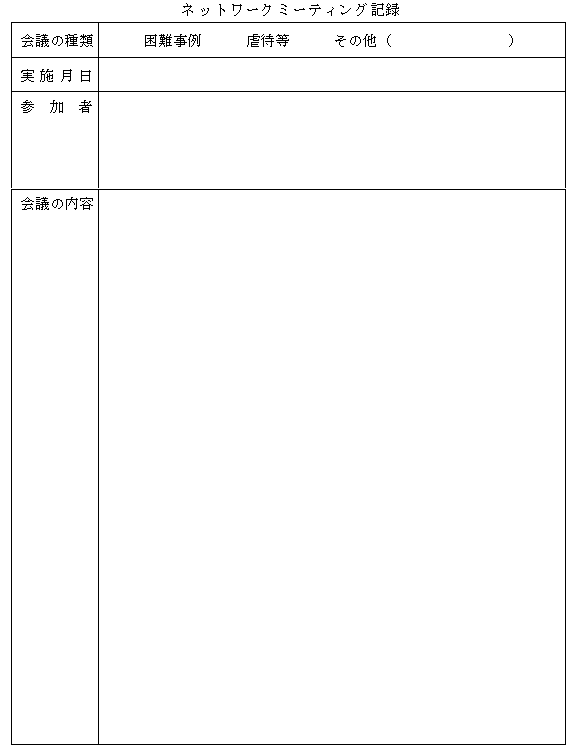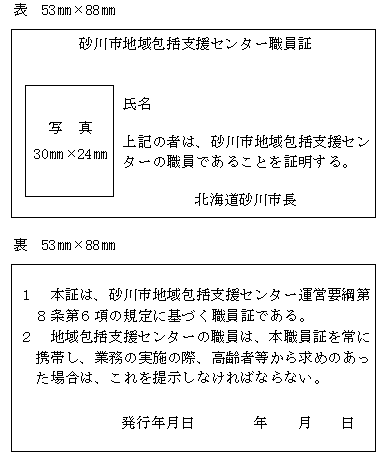第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業を実施する法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)について、その運営に関する必要な事項を定め、センターの円滑な運営を図るとともに、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
2 市は、法第115条の46第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターを設置する法人及びその他市長が適当と認める法人に委託することができる。
3 前項に定める委託を行うに当たっては、砂川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年訓令第36号)第2条第1号イの規定により、砂川市地域包括支援センター運営協議会の意見を聴かなければならない。
第6条 センターが実施する包括的支援事業及びその他の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。なお、これら以外については、「地域包括支援センター業務マニュアル」(平成17年12月19日厚生労働省老健局)及び市の指示に従うこととする。
センターは、法第9条第1号及び第2号のいずれかに該当する高齢者等(以下「高齢者等」という。)の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行わなければならない。
効率的・効果的にセンターの業務を行い、支援を必要とする高齢者等に対し、保健医療福祉サービスを初めとする適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図ること。また、ネットワークの構築に当たっては、サービス提供機関や専門相談機関等のマップの作成等により活用可能な機関、団体等の把握を行うとともに、地域に必要な社会資源がない場合は、その開発に取り組むこと。なお、ネットワーク構築に係る業務を行ったときは、活動報告書(別記第6号様式)に記録すること。
地域におけるネットワークの活用のほか、様々な社会資源との連携、高齢者等への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者等の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行うこと。なお、必要に応じ、基本チェックリスト(別記第1号様式)への記入を求めるとともに、高齢者等の基礎的事項、把握した内容等を、利用者基本情報(別記第2号様式)に記録すること。
(ア) 電話、来所、訪問、FAX等の手段により高齢者等、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じ様々な相談を受け、的確な状況把握等を行うとともに、専門的又は緊急の対応が必要かどうかを判断し、必要な情報を提供し、適切で専門的な機関やサービスにつなげるなど総合的な相談を行うこと。
(エ) 総合相談を実施した際には、必要に応じ、基本チェックリストへの記入を求めるとともに、高齢者等の基礎的事項、把握した内容、相談内容等を利用者基本情報、支援・対応結果を支援・対応経過シート(別記第7号様式)に記録すること。
センターの業務を適切に実施するため、地域においてセンターの役割等を周知するとともに、必要に応じ、権利擁護等に係る啓発活動を行うこと。なお、地域住民に対する広報を行った際には、その内容を活動報告書に記録すること。
センターは、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者等の権利擁護のため必要な援助を行わなければならない。なお、センターが、権利擁護業務を行ったときには、支援・対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。
高齢者に対する虐待の防止及び養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する「養護者」をいう。以下同じ。)の支援について、次の業務を実施すること。また、地域におけるネットワークを積極的に活用し、高齢者に対する虐待の早期発見に努めること。
(ア) 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。また、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずること。
(ウ) 養護者による高齢者虐待に係る通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けるとともに、当該届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、市及び関係機関とその対応について協議を行うこと。
高齢者等、家族、関係機関等からの相談や実態把握によって、その高齢者等の判断能力や生活状況等を把握した結果、医療機関の受診や福祉サービス利用等の契約に関して支援が必要な場合、経済的被害を現に受けている又はその可能性がある場合、預貯金等の財産管理、遺産管理等の支援が必要な場合など、成年後見制度を利用する必要があると判断した場合は、市と連携を図り、必要な支援を行うこと。
高齢者が家族等の虐待又は無視を受けている場合、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合など、保護の必要性があり、老人福祉法に基づく措置が必要であると判断した場合は、市と連携を図り、必要な支援を行うこと。
高齢者等やその家族に重層的な課題が存在している場合、高齢者等自身が支援を拒否している場合、既存のサービス等では適切なものが見つけにくい場合など、その対応が困難な事例を把握した場合には、センターの職員が連携し、対応策の検討を行い、関係機関と連携を図り、必要な措置をとること。
センターは、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による高齢者等の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組みを通じ、当該高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行うこと。なお、センターが、包括的かつ継続的ケアマネジメント業務を行ったときは、地域包括支援センター・ケアマネジメント支援受付票(別記第8号様式)及び包括的・継続的ケアマネジメント支援ネットワークづくり企画書(別記第9号様式)を必要に応じ活用するものとする。
要介護高齢者等に対して包括的かつ継続的な支援を提供していくために、ケアマネジメントの提供に際して、地域の医療機関、介護保険のサービス事業所、介護保険施設、市が行う保健、医療、福祉等のサービスの担当課、地域住民による自主的なボランティア活動やインフォーマルなサービスを実施する機関など、多職種又は多機関が連携するシステムを構築し、サービス担当者会議の開催支援や、入院(所)又は退院(所)時の連携など必要な支援を行うこと。なお、包括的かつ継続的ケアマネジメント体制の構築に係る業務を行ったときは、活動報告書に記録すること。
担当地域の介護支援専門員に対して、そのケアマネジメント力を高めるために次に掲げる必要な支援を行うこと。なお、(ウ)に掲げる相談窓口の開設又は研修の実施を行った場合には、その内容を活動報告書に記録すること。
センターは、高齢者等が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、法第115条の45第1項第2号に定める介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行わなければならない。
対象となる高齢者及びその家族と面接し、介護予防サービス計画の対象となる目標、具体策、利用サービスを決定し、家族やサービス事業所の担当者などと介護予防サービス計画の内容について、共通認識を得ること。なお、当該高齢者が複数のサービスを利用するため、介護予防サービス計画の内容の共通理解を必要とする場合などには、サービス担当者会議(介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)を必要に応じ開催し、開催結果を介護予防支援経過記録(別記第4号様式)に記録すること。
モニタリングは、サービス事業所からの報告又は連絡、サービス事業所への訪問、高齢者からの意見聴取若しくは訪問などにより定期的に実施するとともに、その実施に当たっては、高齢者自身の日常生活能力が社会状況等の変化によって課題が変化していないか、介護予防サービス計画どおり実行できているかを把握すること。なお、モニタリングの結果については、介護予防支援経過記録に記録すること。
サービス事業所からサービス提供後のアセスメントの結果を受け、サービスの実施による効果の評価を行うとともに、モニタリング等の結果を踏まえ、介護予防サービス計画の修正や、再アセスメントの必要性を判断し、次のサービスや事業につなげること。なお、評価の結果を「介護予防支援・サービス評価表(別記第5号様式)に記録すること。
センターは、市が実施する老人保健事業の基本健康診査において、記載された基本チェックリストの内容及び健診の結果等に基づき特定高齢者の候補者と選定された者について、参加することが望ましいと考えられる介護予防プログラムの判定を行わなければならない。また、センターは、何らかの介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された者を特定高齢者として決定し、その結果を市に報告するものとする。なお、センターでの総合相談、実態把握等において、作成された基本チェックリストの内容の結果、特定高齢者の候補者と認められる場合も同様とする。
センターは、認知症地域支援推進員を1名以上配置するものとし、認知症高齢者に適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者及び地域において認知症高齢者を支援する関係者との連携を図り、円滑に事業を推進する体制を構築するとともに、認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、認知症高齢者及びその家族への支援を推進しなければならない。また、認知症初期集中支援推進事業を市及び市立病院とともに推進する。
センターは、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等について、その支援や対応に関わりのある関係者を招集し、課題の解決に向けた援助方法を協議し、関係機関との役割分担のもと、必要な支援を行わなければならない。なお、センターがネットワークミーティングを開催した際には、支援・対応結果を支援・対応経過シート、開催結果をネットワークミーティング記録(別記第10号様式)に記録するものとする。
センターは、高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行うとともに、介護保険制度の利用に関する助言を行うとともに、専門的な観点からの助言が必要と認められる場合は、他の専門職も含め対応の検討を行い、必要な助言を行わなければならない。なお、センターが、担当介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員がいない要介護・要支援認定者について、住宅改修が必要であると判断した場合は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成し、支援又は対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。
(3) センターの開設時間においては、必ず1人の職員は事務室内に残り、相談業務等に対応できる体制をとること。なお、全ての職員の出席が必要な研修又は会議の場合、緊急時の対応を行う場合は、この限りではない。
第10条 センターは、個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。
3 指定介護予防支援事業者が、介護予防支援の業務について、法第115条の23第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、委託範囲、委託先等については、市の方針に従うものとする。