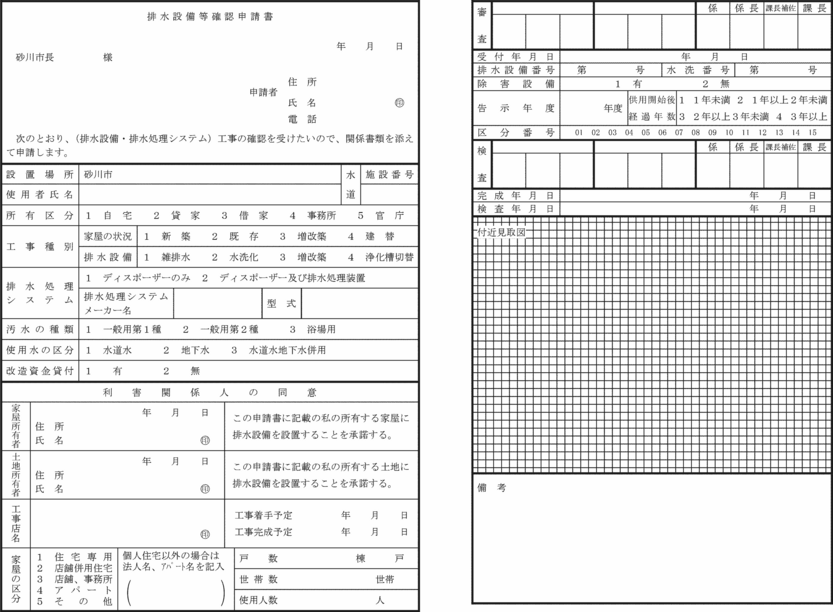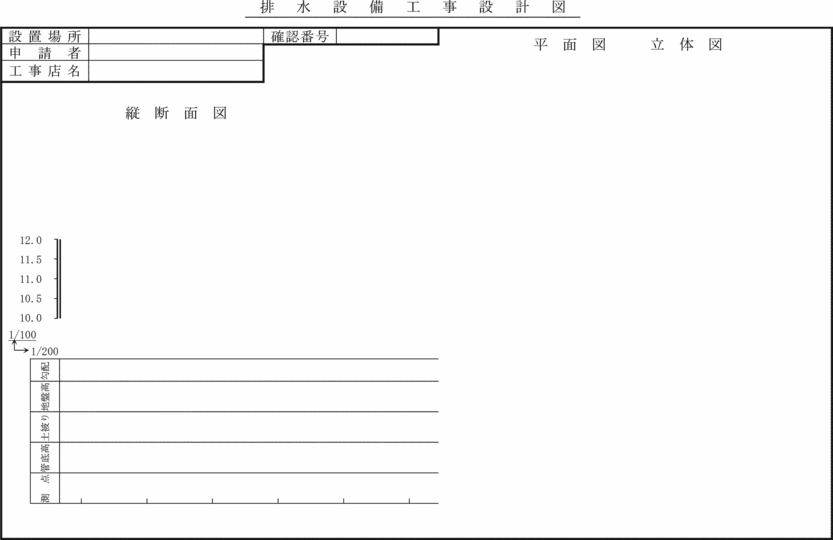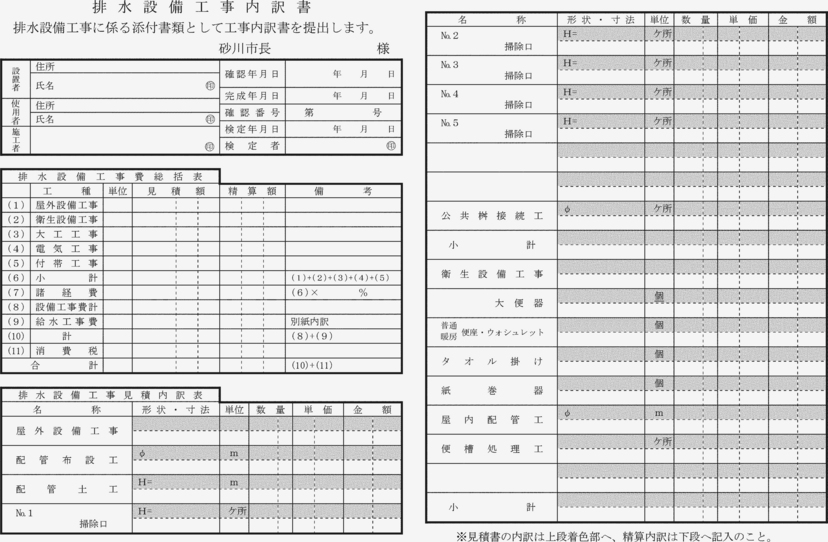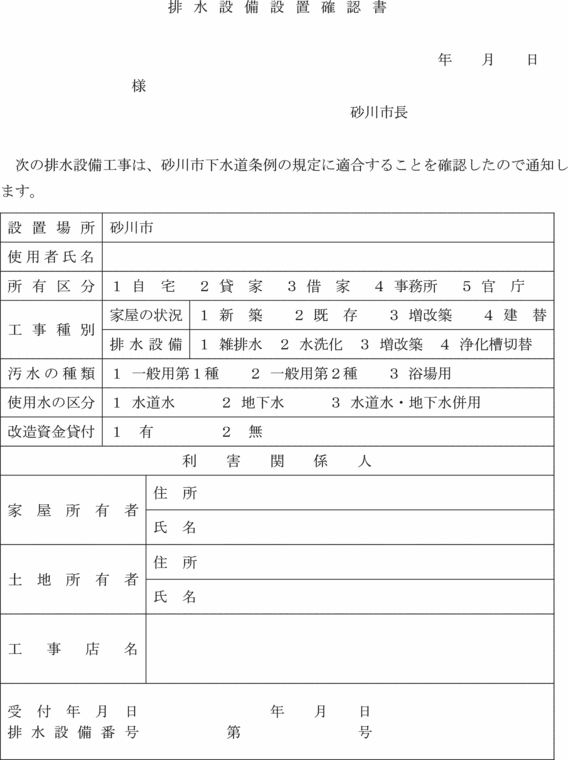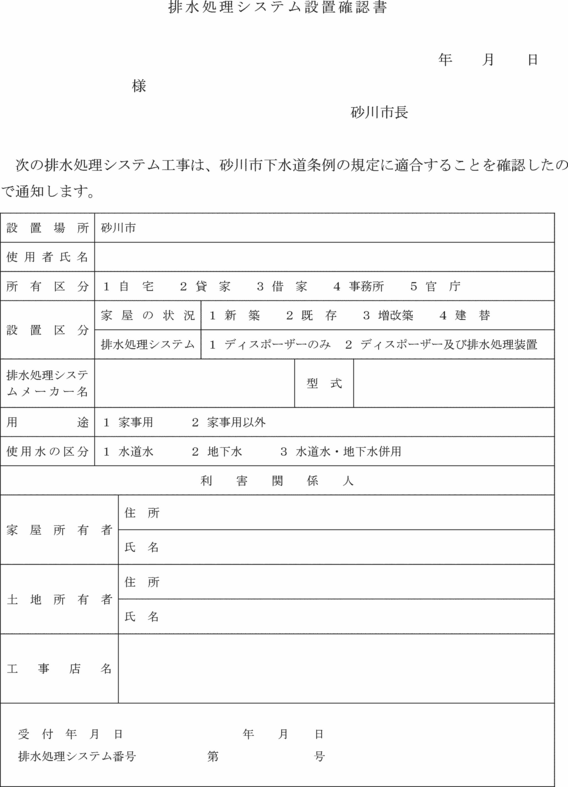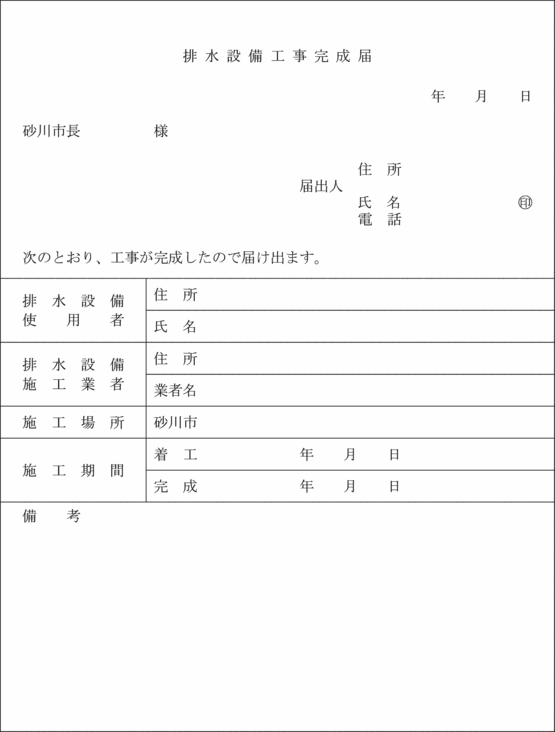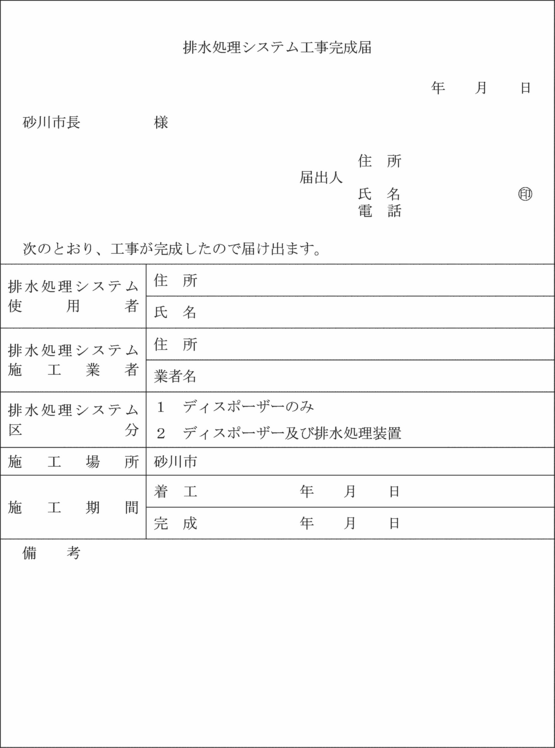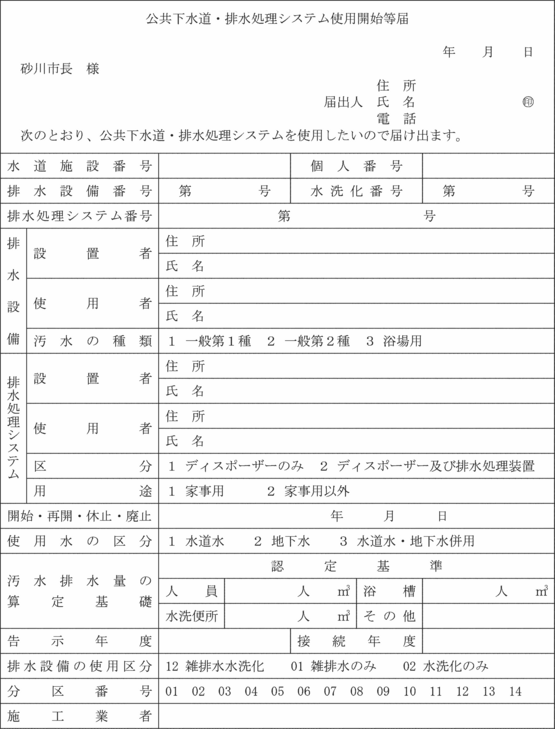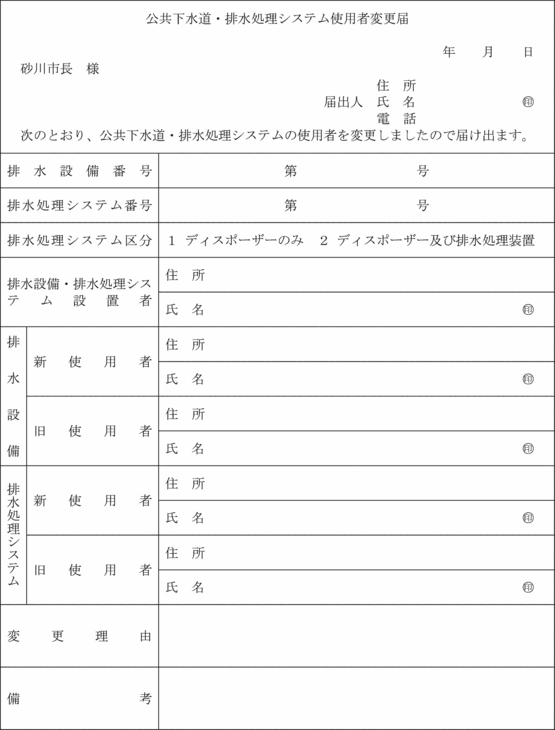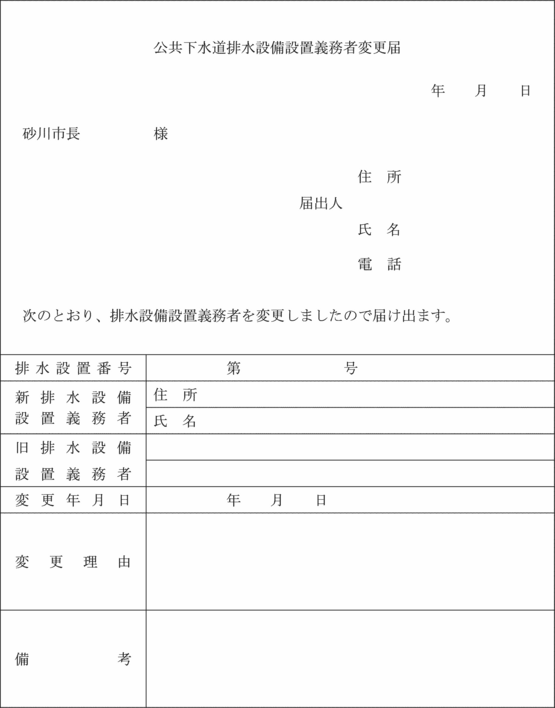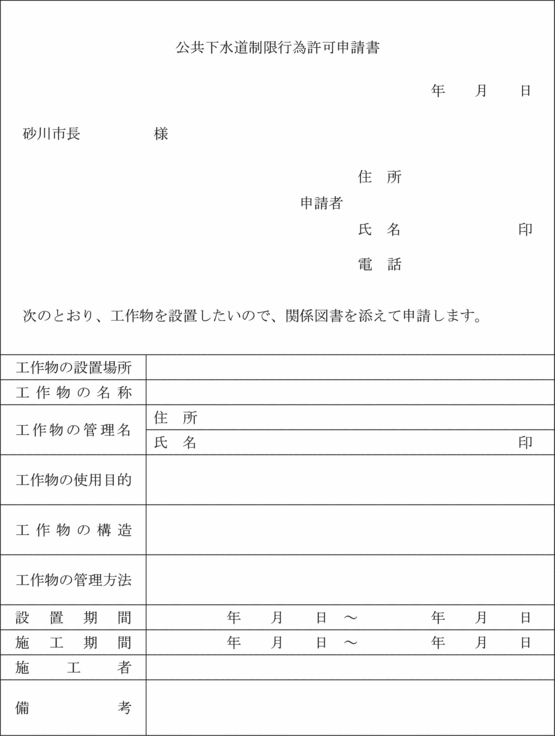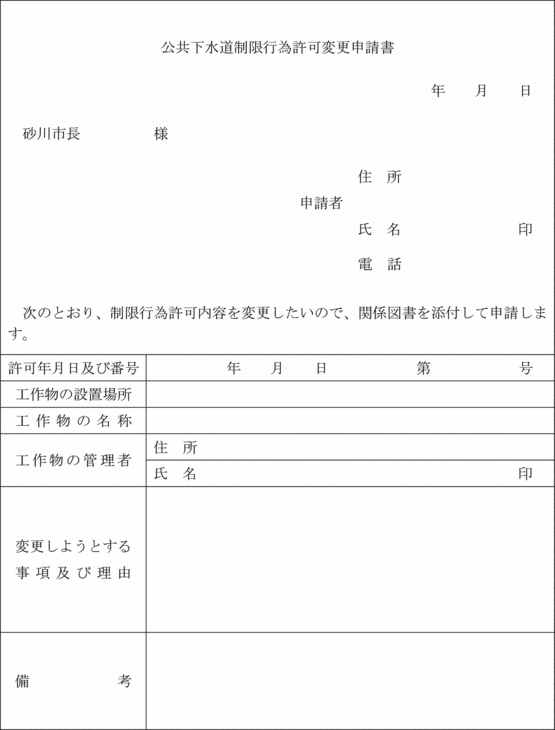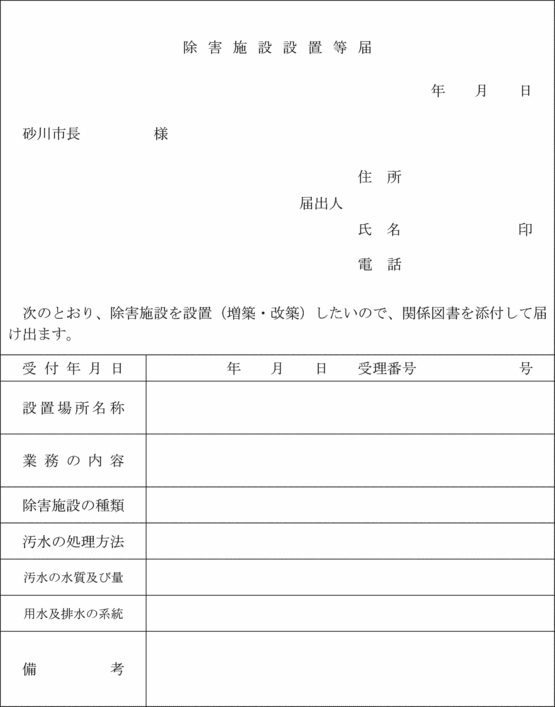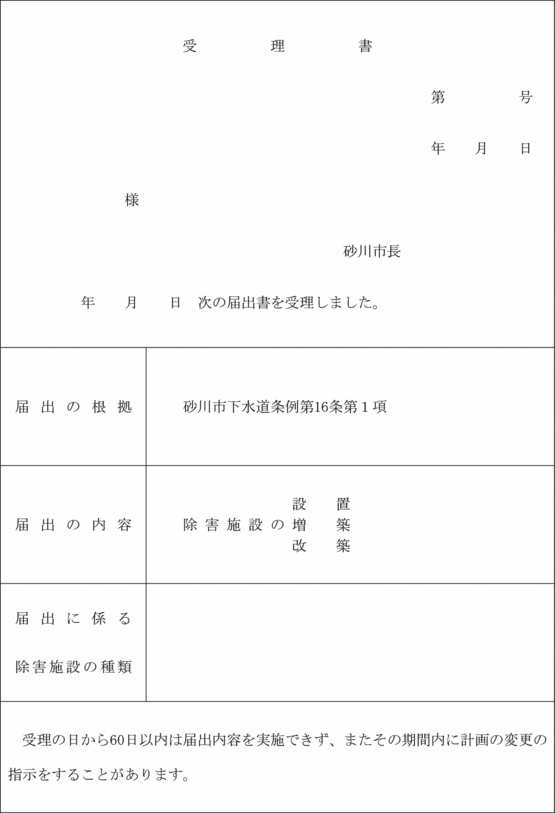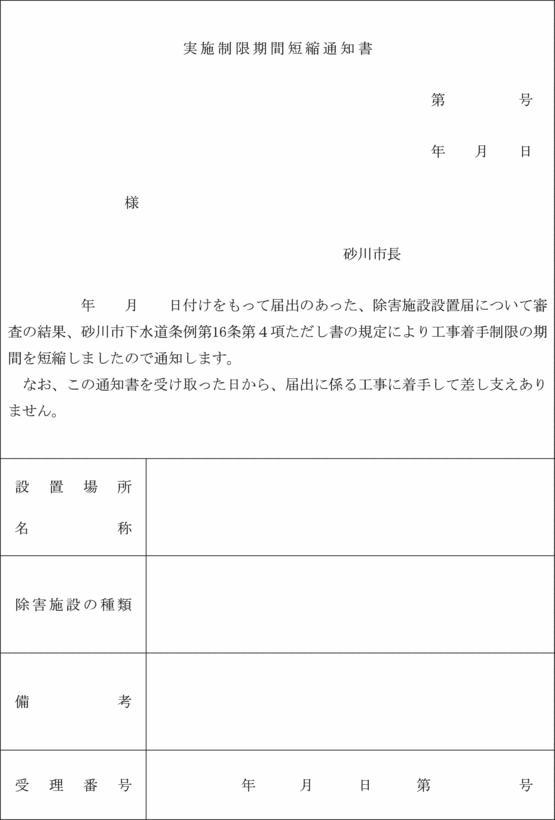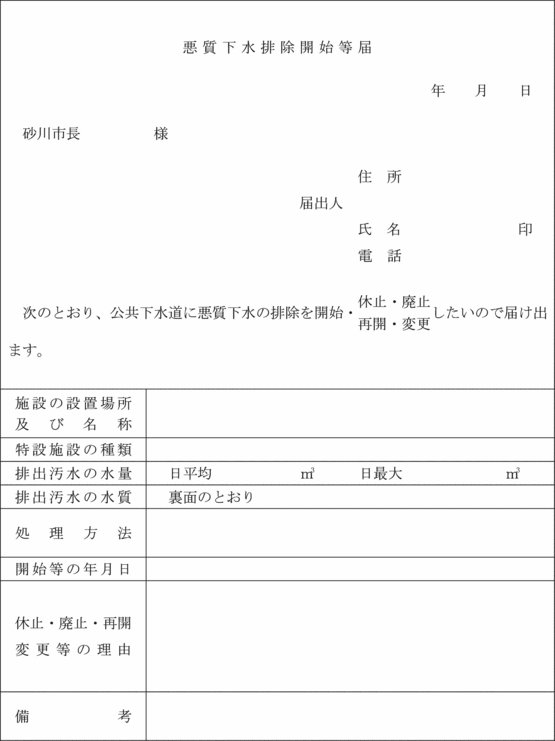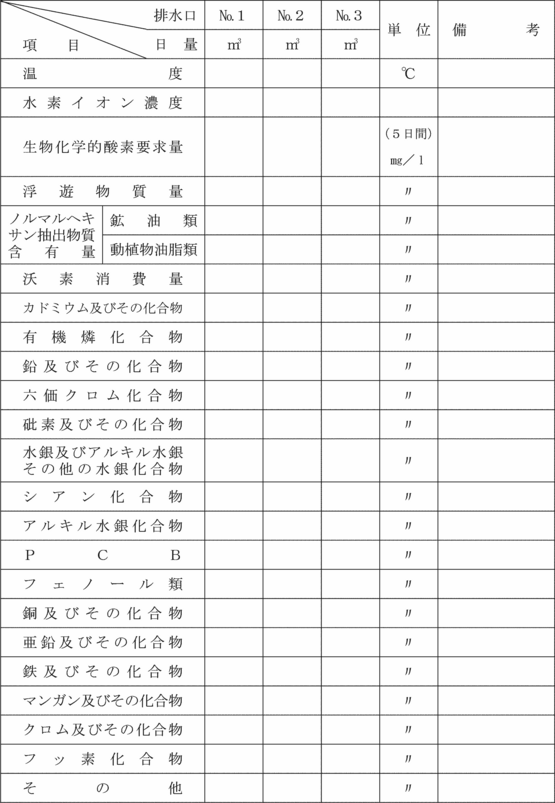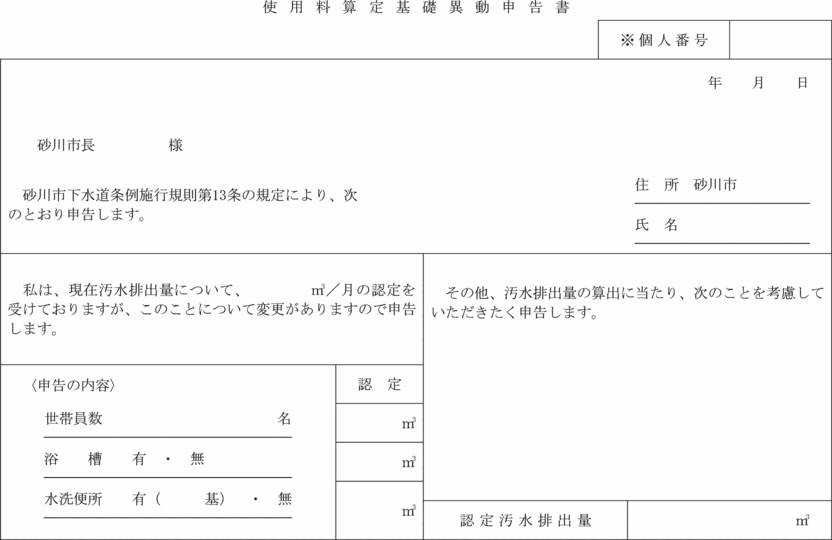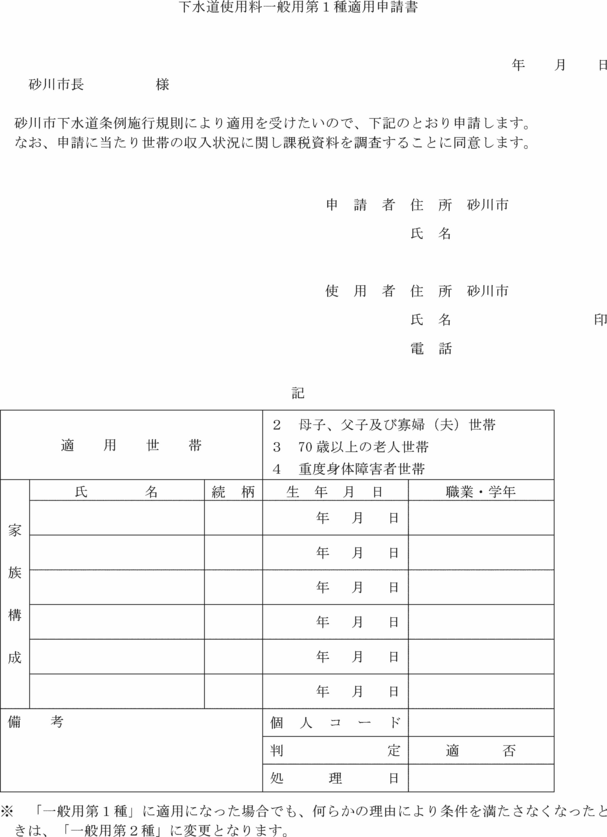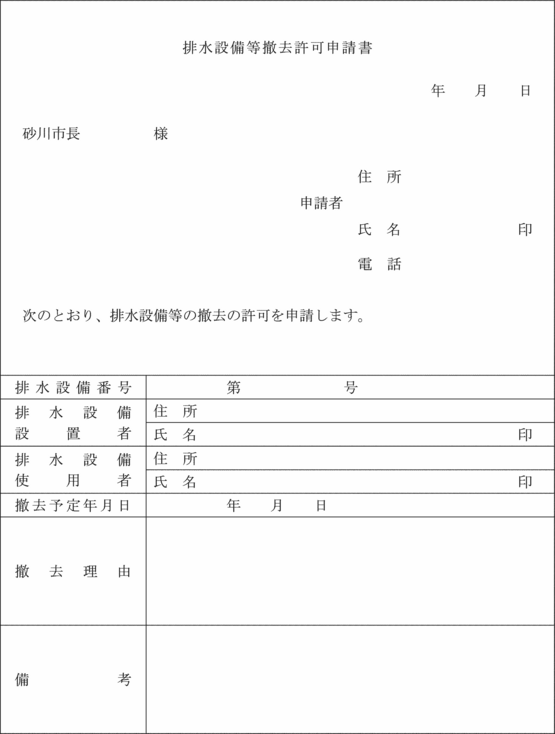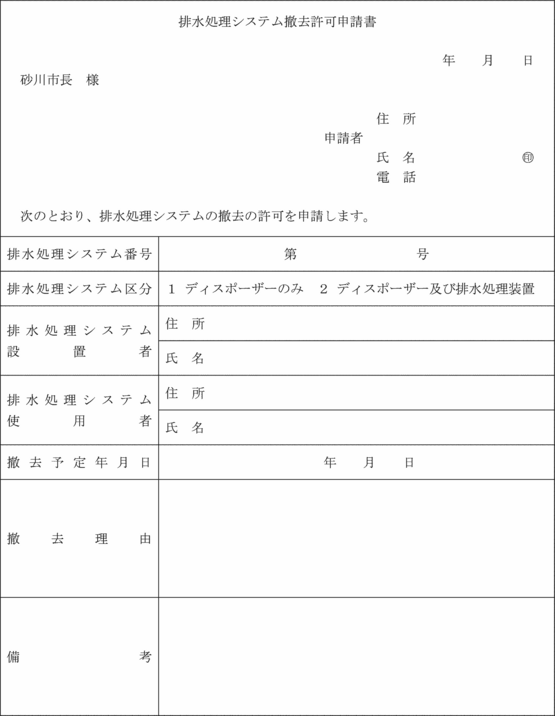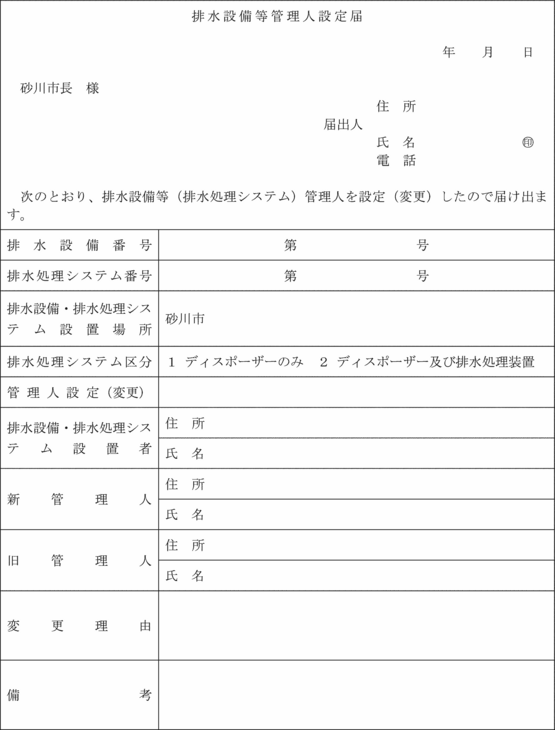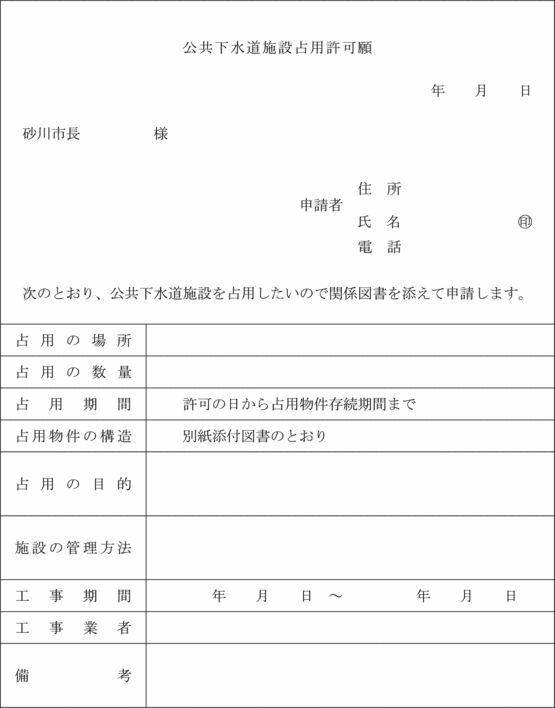第1条 この規則は、
砂川市下水道条例(昭和60年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか市長が別に定める砂川市排水設備設計施行要綱による。
第3条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 見取図 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等を明示すること。)、排水箇所、既設の排水設備、公共下水道等
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は100分の1を標準とし、管渠の大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管渠の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1以上とし、管渠及びその附属装置の構造並びに寸法を表示すること。
(5) 承諾書 他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。
(1) 排水処理システムを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
ア 下水道使用料、市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金を滞納していないこと。
イ 他人の土地又は排水設備を使用しなければ排水処理システムから排除された汚水を公共下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ること。
(2) 排水処理システムにあっては、公益社団法人日本下水道協会が定める下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)に基づき同協会の製品認証を受けたものであり、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。
第3条の3 条例第6条の2第1項の規定により排水処理システムの新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、排水処理装置を設置する者にあっては、適合評価書の写し、装置の仕様書(算定根拠を含む。)及び維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写しを添付すること。
2 前項の申請書には、新設の場合に限り、第3条第2項第1号から第4号までに掲げる図面その他市長が必要があると認める図面を添付しなければならない。
第4条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、
条例第4条又は
第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、その旨を排水設備設置確認書(
別記第2号様式)により当該申請者に通知する。
2 市長は、第3条の3の規定による申請があったときは、第3条の2の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、その旨を排水処理システム設置確認書(
別記第2号様式の2)により当該申請者に通知する。
3 前2項の場合において、審査の結果
条例第4条又は
第5条若しくはこの規則の第3条の2の規定に適合しないと認めたときは、市長は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(排水設備等又は排水処理システム工事の完了届及び検査)
第5条 条例第8条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事が完成したときは、排水設備工事完成届(
別記第3号様式)を市長に提出し、
条例第7条に規定する公認業者立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。
2
条例第8条第1項に規定する排水処理システムの新設等の工事が完成したときは、排水処理システム工事完成届(
別記第3号様式の2)を市長に提出し、
条例第7条に規定する公認業者立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。
3 公認業者は、工事完成後1年以内に生じた故障については、その公認業者の費用でこれを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因する場合は、この限りでない。
第6条 市長は、前条の検査(排水設備等に係る検査に限る。)の結果適当と認めたときは、排水設備等施工済章標(
別記第4号様式。以下「施工済章標」という。)を交付する。
2 施工済章標を交付されたときは、当該建築物の門戸その他見やすい箇所にこれを掲示しなければならない。
3 施工済章標を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
第7条 条例第10条の規定により、公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、公共下水道・排水処理システム使用開始等届(
別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
2 公共下水道又は排水処理システムの使用者が変更になったときは、前項の規定にかかわらず公共下水道・排水処理システム使用者変更届(
別記第6号様式)により新旧使用者が連署して届け出なければならない。
第8条 排水設備設置義務者が変更したときは、公共下水道排水設備設置義務者変更届(
別記第7号様式)により、新旧排水設備設置義務者が連署して市長に届け出なければならない。
第9条 条例第11条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道制限行為許可申請書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共下水道制限行為許可変更申請書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、受理書(
別記第11号様式)を届出者に交付しなければならない。
第13条 条例第20条第4項に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者のする申告又は公共下水道の使用者が汚水排水量認定の基準となる事項に変更を生じたとき、その他使用料算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(
別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
第14条 条例第2条第1項第14号に定める生活保護世帯、母子、父子及び寡婦(夫)世帯、70歳以上の老人世帯並びに重度身体障害者世帯とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、4月から6月までの定例日に係る使用料については、
条例第2条第1項第14号中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
(1) 生活保護世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯で、かつ、公共下水道の使用者として届出されている者
イ
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳の交付を受けている者で、その判定がAのもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)による1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 70歳以上の老人世帯 70歳以上の老人単身世帯、夫婦のいずれかが70歳以上の世帯又は70歳以上の者が同居する親族を扶養している世帯で、かつ、公共下水道の使用者として届出されている者
(4) 重度身体障害者世帯
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者の収入で生計を維持している世帯で、かつ、公共下水道の使用者として届出されている者
2 前項第2号、第3号及び第4号の適用を受けようとする者は、下水道使用料一般用第1種適用申請書(
別記第15号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(排水設備等又は排水処理システムの撤去の許可の申請)
第18条 条例第8条第1項、
第25条第1項の規定により職員が検査を行うときは、市長の発行する身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別記第1号様式
(第3条関係)
別記第2号様式
(第4条関係)
別記第2号様式の2
(第4条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第3号様式の2
(第5条関係)
別記第4号様式
(第6条関係)
別記第5号様式
(第7条関係)
別記第6号様式
(第7条関係)
別記第7号様式
(第8条関係)
別記第8号様式
(第9条関係)
別記第9号様式
(第9条関係)
別記第10号様式
(第10条関係)
別記第11号様式
(第10条関係)
別記第12号様式
(第11条関係)
別記第13号様式
(第12条関係)
別記第14号様式
(第13条関係)
別記第15号様式
(第14条関係)
別記第16号様式
(第15条関係)
別記第16号様式の2
(第15条関係)
別記第17号様式
(第16条関係)
別記第18号様式
(第17条関係)